ETFは上場投資信託といい、証券取引所で取引される投資信託のことですが、投資信託との違いって何でしょうか?
投資信託への投資を考えネットで調べているとETFという商品があることを目にすることも多いので気になっている方も多いと思いますので、投資するならどっちがいいかまとめてみました。
参考 ETFとは?コストは安いが投資する上でのメリット・デメリットは?
ETFと投資信託の違い
ETFはTOPIXや日経平均などのインデックスに連動した動きを目指す商品で、投資信託でのインデックスファンドとかなり似た金融商品ですが下記のような違いがあります。
| ETF | インデックスファンド | |
| 売買場所 | 証券会社 | 証券会社、銀行、郵便局など |
| 売買価格 | リアルタイムに売買 | 1日1回 |
| 売買手数料 | 証券会社の株式売買手数料による | 多くは0%(購入時手数料) ※売却時に信託財産留保額が 必要なファンドもある |
| 信託報酬 | 投資信託より安い | 0.1%以下~0.3%程度 |
| 最低投資金額 | 数千円から | ネット証券なら100円から |
| 分配金 | 元本払戻金(特別分配金)はない | 元本払戻金(特別分配金)となる場合がある |
| 分配金自動再投資 | できない | できる |
| 自動積立 | 基本できない (一部のネット証券で可能) |
できる |
売買場所
ETFは通常の株式と同様に上場しているので、株式と同じように取引所で売買することができ、各証券会社を通して売買することができます。
投資信託は、証券会社だけでなく銀行や郵便局などでも購入することはできますが、ネット証券以外は購入時手数料が必要な場合もあり、信託報酬が高コストな投資信託が多いので注意してください。(同じファンドでもネット証券では購入時手数料が必要ないような場合もあります)
売買価格
ETFは株式同様に市場が開いている間はリアルタイムに売買価格が変動します。
投資信託の価格は基準価額と呼ばれ、市場が終わった後に投資信託が保有している株式や債券などの時価を1日に1回計算され価格が決まります。(ETFにも基準価額があります)
そのため、注文してから価格が決まるまでの間のニュースなどにより価格が変動してしまうと、思い通りの価格で購入ができないといった可能性があります。
売買手数料
ETFは通常の株式と同じ扱いなので、株式同様の売買手数料がかかります。
SBI証券
や
楽天証券
なら簡単な手続きをするだけで売買手数料が無料となり、三菱UFJ eスマート証券や岡三オンラインなら約定代金が100万円以下まで手数料が無料と、少額から初心者の方でも気軽に投資ができます。
参考 【国内株式・ETF】ネット証券口座おすすめ比較ランキング!手数料が安いのは?
投資信託は購入時手数料がかからないノーロード投資信託というものがあり、特に信託報酬が低コストなインデックスファンドの多くは購入時手数料が無料となっています。
下記のネット証券では、他の金融機関で購入時手数料が必要なファンドでも購入時手数料を無料としているので、銀行などで投資する前に下記のネット証券で投資しようとしているファンドを取り扱っているかチェックしたほうがお得です。
- SBI証券
- 楽天証券
- マネックス証券
- 三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)
- 松井証券
- 岡三オンライン証券
参考 【投資信託】ネット証券おすすめ比較ランキング!お得な口座は?
信託報酬
信託報酬は、ETFでも投資信託でも保有している間に常にかかるコストとなりますが、ETFの魅力といえば保有時にかかるコストである信託報酬が低コストなものが多いという特徴があります。
例えばTOPIXをベンチマークとする「iシェアーズ・コア TOPIX ETF(1475)」の信託報酬は0.0495%(税込)です。
参考 【1475】iシェアーズ・コア TOPIX ETFの評判や評価ってどう?利回りはどのくらい?
投資信託は最近では低コストインデックスファンドが出ていますが、TOPIXをベンチマークとした投資信託では最安値は「eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)」の0.143%(税込)ですので、約3分の1しかコストはかかりません。
参考 国内株式インデックスファンド(投資信託)を比較!おすすめは?
ETFは売買手数料がかかりますが、信託報酬はファンドを保有している間ずっとかかるコストとなるので、これだけのコスト差があるので長期になればなるほどETFの方がコストメリットが出てきます。
最低投資金額
例えば「iシェアーズ・コア TOPIX ETF」の購入は10口からなので、約3,000円から投資することができますが、他のETFでも大体1万円前後で購入できるものが多くあります。
投資信託はネット証券なら一括でも積立でも100円から購入できることを考えると、ETFは多少投資金額が必要です。
分配金
低コストなインデックスファンドでは分配金を出さないファンドが多いので、ファンドで投資している株式や債券などから得られた利子や配当、売買益などを分配せず、さらに運用に回すことにより複利効果が期待できます。
また、分配金を出す投資信託では普通分配金と特別分配金というただの元本払戻金の分配金があります。
毎月分配型などでは、ファンドで得た利益以上に特別分配金を多く支払うことによって見た目上の分配金利回りが上がっているファンドがあり、この分配金はただ単に自分が投資したお金が戻ってきているだけなので、何の意味もない分配金です。
ETFは原則決算時に運用期間中に得られた配当や利息などの収益から信託報酬などのコストを差し引いて残りはすべて分配することが法律で定められているので、投資信託のような無意味な分配金ではなく一生得られる不労所得となってくれます。
分配金再投資
投資信託は分配金を出す投資信託と出さない投資信託があります。
分配金を出さない投資信託は、投資した株式や債券などの配当金などの収益は投資信託の資産として自動で再投資されるので、複利効果が期待でき中長期的に資産を増やしてくれる期待ができます。
分配金を出す投資信託は、証券会社の設定でそのまま分配金を受け取れたり、自動で分配金を再投資する設定を選ぶこともできますが、再投資する分配金は課税されるので、その分再投資される資金が少なくなるのでそもそも分配金を出さないほうが資産形成には有利です。
投資信託の分配金には「普通分配金」「元本払戻金(特別分配金)」があり、分配金を出す投資信託の中には「元本払戻金」を多く出している投資信託がありますが、「元本払戻金」はその名の通り投資した資金が戻ってきているだけの分配金となります。
運用をしたいと資金を投資しているのに、その資金の一部が戻ってきているだけと意味のない分配金ですが、これを行うことにより運用成績は良くないが見かけ上の分配金利回りが高い投資信託というのが存在するので、そのような投資信託への投資は控えるのが賢明です。
参考 投資信託の分配金利回りランキングはあてにならない?日本証券業協会から注意喚起!
ETFの分配金は、原則ETFの運用で得られた利益を分配するので健全な分配金ですが、分配金を自動で再投資する仕組みがないので、再投資したい場合は手動で行う必要があります。
米国ETFが対象ですが、マネックス証券では「配当金再投資サービス」を利用することによってETFの分配金を自動で再投資することが可能です。
>> マネックス証券(公式サイト)
自動積立
資産運用の王道は「長期・積立・分散」と言われていて、その一つでもある「積立」を行うことにより、相場を気にせずいつでも始められ、毎月定額で購入すればドルコスト平均法によりリスクを軽減効果が期待できます。
毎月積立するといっても、忙しくて積立するの忘れたといったことはよくあることですが、自動で積立できれば積立忘れを防ぐことができます。
投資信託では、多くのネット証券で自動積立に対応していて、手数料無料で銀行から定期的に積立金額を引き落としてくれるので、手軽に長期積立が可能です。
一方ETFではauカブコム証券などで自動積立は可能ですが、あまり自動積立に対応しているネット証券はほとんどないため、基本的には手動での積立となるので手間がかかります。
米国ETFでは、SBI証券とマネックス証券が自動積立に対応しているので、ドルコスト平均法にて米国ETFを購入することができます。
結局投資信託とETFはどっちがお得?
ETFは投資信託と比べて
ということになります。
ETFは信託報酬が低コストということですが、どのくらい差が出るものでしょうか?
例えば100万円をTOPIX連動型の「iシェアーズ・コア TOPIX ETF(1475)」と「eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)」に10年間投資した場合を比較すると下記のような感じとなります。(正確には100万円ぴったり買うことにはなりませんが概算として約100万円分購入した場合で算出)
| 売買手数料 | 年間コスト(税込) | 10年間のコスト | |
| iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 0円 | 0.0495×100万=495円 | 4,950円 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0円 | 0.143%×100万=1,430円 | 14,300円 |
※ETFの売買手数料はSBI証券や楽天証券の無料の手数料を想定
参考 【国内株式・ETF】ネット証券口座おすすめ比較ランキング!手数料が安いのは?
ETFのは売買手数料がかかりますが、SBI証券や楽天証券では簡単な手続きをするだけで売買手数料が無料なので、ETFで健全な分配金・配当金を受け取りたいならETFも選択肢となります。
海外ETFはどう?
海外ETFは主に海外市場に上場するETFで、国内のネット証券ではSBI証券、楽天証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)で取引することができます。
参考 【海外株式・ETF】ネット証券口座おすすめ比較ランキング!手数料が安いのは?
海外ETFは外国株と同様に外貨での投資となるため、円を外貨に交換するために為替手数料が必要で、売買手数料も国内ETFなどと比べるとやや高めです。
ただ、バンガード社やブラックロック・グループが運用する「iシェアーズ(iShares)」など世界レベルのETFは信託報酬が激安のものがあります。
例えば、全世界の株式市場に分散できる「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」の信託報酬は0.191%(税込)と低コストではありますが、そのファンド内で実質的に投資している「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)」の経費率(実質コスト)は大きく下回る0.07%と超低コストとなっています。
参考 【VT】バンガード・トータル・ワールド・ストックETFの評価・評判とは?利回りや配当金はどのくらい?
参考 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)の評判や評価って?利回りや実質コストは?
また、海外ETFの中でも米国ETFは売買手数料、為替手数料がかかりますが、NISA口座を利用すれば売買手数料を無料にできたり、分配金の二重課税を解消できるというメリットがあります。
参考 米国ETFをNISAで購入するメリットやデメリットとは?
CFDという選択肢も!
投資信託の中でも日経平均やNYダウといったインデックスと連動する投資信託のことをインデックスファンドと言いますが、ETFも基本的には何かしらのインデックスに連動する動きとなります。
その中でも特に日経平均やNYダウ、S&P500といったメジャーなインデックスに投資するならCFDという選択肢もありまし、それぞれの特徴は下記となります。
- 投資信託:100円と少額から自動積立できるので長期資産運用に向いている
- ETF:健全な配当金・分配金を得ながらNYダウ自体の値上がりを期待できる
- CFD:資金の数倍の取引を買いも売りも簡単に行え特に短期売買に向いている
CFDは短期売買だけでなく長期売買もでき、特に自己資金の何倍もの取引ができるレバレッジを利用した取引が簡単にできる点が大きな特徴の一つです。
CFDの一つの分類がFXなので、レバレッジを利用できるなど仕組み自体はほとんど同じです。
参考 FXのレバレッジとは?レバレッジ1倍でも借金することはある?
また、FX同様に買いだけでなく売りも簡単に投資できるので、値下がりしそうな時にも素早く取引ができ利益を得ることも可能です。
まとめ
投資信託とETFの違いとして、ETFは下記のような特徴が挙げられます。
- 売買手数料がかかる
- 信託報酬は安い
- 分配金の再投資や積立は手動で行う必要がある
SBI証券
や
楽天証券
なら簡単な手続きをするだけで売買手数料が無料となり、三菱UFJ eスマート証券や岡三オンラインなら約定代金が100万円以下まで手数料が無料と、少額から初心者の方でも気軽に投資ができます。
参考 【国内株式・ETF】ネット証券口座おすすめ比較ランキング!手数料が安いのは?
ETFの自動積立は、一部の国内ETFであれば三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)で可能で、米国ETFであればSBI証券・マネックス証券で可能となっています。
参考 auカブコム証券の評価・評判ってどう?メリット・デメリットのまとめ
参考 米国株の積立投資ができる米国株式・ETF定期買付サービスとは?デメリットは?
ただ、売買手数料がかかる証券会社で取引するとコストが割高となるので気になる方は一括で投資したほうが低コストとなります。
また、ETFの分配金の再投資は自動で行われないので、長期にわたって複利効果を享受するためには手動で行わなければいけないといった手間がかかり、頻繁に行うことでもないので長期投資だと忘れがちとなってしまう点がデメリットです。(米国ETFならマネックス証券で分配金を自動で再投資してくれます)
投資信託なら100円から自動で積立でき、分配金を出さないインデックスファンドならファンド内部でさらに運用されることによって複利効果も期待できるので、ある程度割り切ってコストの差は自動化の必要経費と思ってインデックスファンドに投資するのもありかと思います。
もちろんコストをかけたくない方は手動で再投資をすればリターンは良くなるので、どちらを選ぶかは個々の考え方次第かと思います。
投資信託を購入するのにおすすめの証券会社はどこ?
各ネット証券では投資信託に関して保有残高に応じたポイント還元と、クレジットカード積立によるポイント還元があります。(保有残高によるポイント還元もクレジットカード積立もNISA口座も対象)
参考 投資信託でポイントが貯まるネット証券を比較!おすすめはどこ?
松井証券(公式サイト)はクレカ積立に対応していませんが、投資信託保有時のポイント還元率は最高水準となっています。
クレジットカード積立のポイント還元率は、年会費がかかるカードであれば SBI証券 が最高水準ですが、実質年会費がかからない一般カードであればマネックス証券が最高水準です。
トータルのポイント還元率が業界最高水準のマネックス証券

- 保有残高によるポイント還元率(低コストファンド):0.03%(一部0.03%未満もあり)
- クレジットカード積立によるポイント還元率:1.1%
クレジットカード積立を利用し、トータルのポイント還元率が業界最高水準なのがマネックス証券です。
クレジットカード積立で必要なマネックスカードは、マネックス証券を口座開設すれば作ることができ、1回以上クレジットカードの利用があれば無料となり、投信積立でも対象となるので、積立している間は費用は掛かりません。
貯まったポイントは株式手数料や暗号資産に交換することや、他のポイントサービス(dポイント・Tポイント・Pontaポイントなど)に交換することも可能です。
保有残高によるポイント還元率が高くクレカ積立もできるSBI証券

- 保有残高によるポイント還元率(低コストファンド):0.0175%~0.063%
- クレジットカード積立によるポイント還元率:0.5%(一般カード)
ゴールドカードなら1%・プラチナカードなら2%・プラチナプリファードなら5%
投資信託の保有残高によるポイント還元率は高水準で、低コストな投資信託にクレジットカード積立を利用しない場合にはおすすめです。
クレジットカード積立で一般カードだと還元率は低いですが、ゴールドカードは年間で100万円以上利用すれば翌年以降の年会費永年無料となるので条件クリアできそうであればゴールドカードの方がおすすめです。(ただしクレジットカード積立は集計対象外です)
>> 三井住友カード(NL)
保有残高によるポイント還元率が業界最高い水準の松井証券
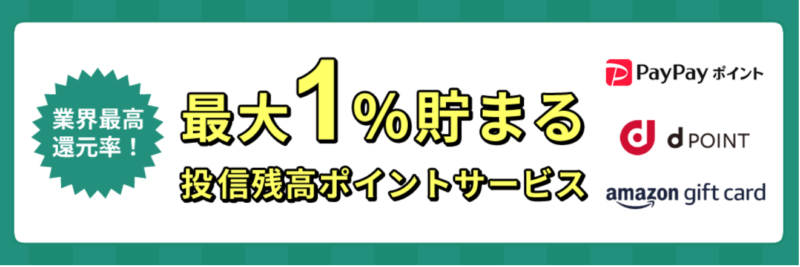
- 保有残高によるポイント還元率:0.01%~1%
- クレジットカード積立によるポイント還元はなし
松井証券は投資信託の保有残高によるポイント還元率がどの投資信託も業界最高水準です。
クレジットカード積立によるポイント還元がないので、クレジットカード積立を利用しない方にはおすすめです。
松井証券では、他の金融機関で保有している株式や投資信託を待つ証券に移管する際に、移管元の金融機関に支払った手数料を全額負担してくれるので実質無料で移管することができ、移管後は投資信託の保有残高によるポイント還元を受けることができます。
Pontaポイントが貰えるauカブコム証券

- 保有残高によるポイント還元率(低コストファンド):0.005%(一部0%)
- クレジットカード積立によるポイント還元率:1%
投資信託の保有残高によるポイント還元は低いのですが、クレジットカード積立によるポイント還元率は1%と高めの還元率です。
スマホでauを利用していると貯めやすいPontaポイントが貯まり、auじぶん銀行と連携すれば普通預金の金利が年率0.1%となり、au Payなどとも連携すれば0.2%になる点もメリットがあります。
またauマネ活プランに入ればauじぶん銀行の普通預金の金利が最大0.3%になったり、クレジットカード積立によるポイント還元率が最大3%とさらに優遇されます。
>> 三菱UFJ eスマート証券(公式サイト)「詳細解説」
楽天ポイントが貰える楽天証券

- 保有残高によるポイント還元率:ー(4つのファンドのみポイント還元あり)
- クレジットカード積立によるポイント還元率:0.5~1%(一般カード)
ゴールドカードなら0.75%~1%・プレミアムカードなら1%・
楽天証券では、保有残高によるポイント還元率が「一定の残高をはじめて達成した場合」のみポイントが還元されるルールに変更され、実質保有残高によるポイント還元はほぼなくなりました。
クレジットカード積立は一般カードで低コストなファンド(※)は0.5%でその他のファンドは1%となっています。
※代行手数料が年率0.4%(税込)未満のファンド
楽天ポイントは楽天経済圏では貯めやすく、様々なサービスで利用できるので、楽天ポイントを貯めたい方は楽天証券という選択肢もあるかと思います。
>> 楽天カード(公式サイト)
今利用している証券会社から他の証券会社に投資信託などは移管することが可能です。
通常は移管元の証券会社で手数料が必要になりますが、下記のネット証券なら移管元で支払った移管手数料をキャッシュバックしてくれるので実質無料で移管することができます。
投資信託に投資するのにおすすめの証券会社は?
ネット証券では投資信託に関するポイント還元など様々なサービスを行っていますが、どのような違いがあるのか、おすすめはどこかは下記も参考にしてみてください。
参考 【投資信託】ネット証券おすすめ比較ランキング!お得な口座は?
国内ETFを購入するのにおすすめの証券会社は?
約定代金が100万円以下なら手数料が無料のSBI証券か楽天証券、岡三オンラインがおすすめです。
もちろん口座開設・維持費用は無料です。
>> SBI証券 (公式サイト)[詳細解説]>> 楽天証券 (公式サイト)[詳細解説]
>> 岡三オンライン (公式サイト)
国内株式・ETFで失敗しない証券会社選び!
これから国内株式・ETFで資産運用を始める方は、ネット証券選びで失敗しないようにこちらも参考にしてみてください。
参考 おすすめネット証券比較(国内株式・ETF編)!手数料だけで選ぶ?
海外株式、ETFを購入するのにおすすめの証券会社は?
売買手数料、為替手数料のトータルコスト最安値のSBI証券!米国株式、ETFでは業界唯一の貸株サービスや自動積立も行うことができます。もちろん口座開設・維持費は無料です。
>> SBI証券 (公式サイト)
参考 SBI証券の米国ETFでの貸株サービスや自動積立については下記も参考にしてみてください。
⇒ SBI証券の米国貸株サービスの金利ってどのくらい?海外ETFも対象!
⇒ 米国株式・ETF定期買付サービスとは?NISAを有効に活用するには?
米国株、中国株の取り扱い銘柄は業界No1!しかも米国株・ETFの自動積立や配当金を自動で再投資することも可能です。もちろん口座開設・維持費は無料です。
>> マネックス証券 (公式サイト)海外ETFや海外株式を始める方は、ネット証券選びで失敗しないようにこちらも参考にしてみてください。
参考 【海外株式・ETF】ネット証券口座おすすめ比較ランキング!手数料が安いのは?米国株・ETFでは為替変動リスクがありますが、リスク軽減策については下記を参考にしてみてください。
参考 米国株への投資は為替変動リスクが気になる?軽減する方法はある?CFDを購入するのにおすすめな証券会社は?
手数料無料で取り扱い商品も多く、少額取引をしたいならGMOクリック証券
口座開設・維持費は無料ですし、既にGMOクリック証券に口座を持っていれば簡単にCFD口座を開設することができます。
>> GMOクリック証券【CFD】(公式サイト)[詳細解説]
店頭CFDで商品は少なくシンプルなのがいいならDMM.com証券
取扱銘柄は7つと少ないので、商品選びに迷わなくて済みます。もちろん口座開設・維持費は無料です。
>> DMM CFD(公式サイト)
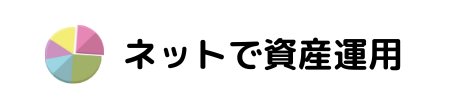
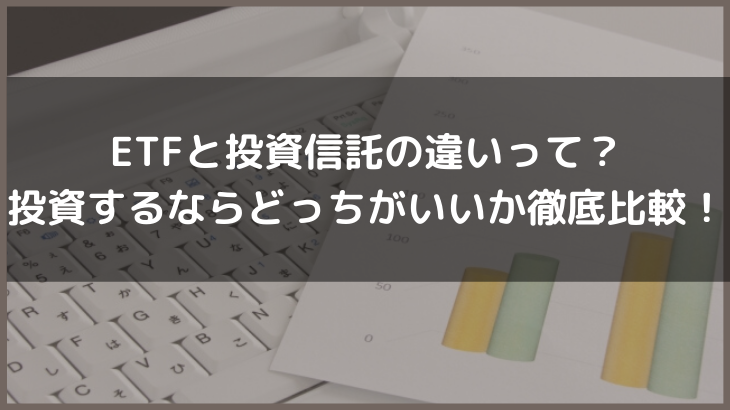
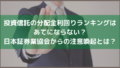

ドルコスト平均法とは、日々価格が変わる金融商品を定期的に定額で購入する投資手法のことです。相場が高い時には少なく、相場が低い時には多く購入することにより平均購入単価が平準化されるメリットがあります。